このブログでは、不動産投資のコツを初心者の方向けに解説しています。

マンション経営に興味があります。
最初にどれくらいの資金が必要か教えてください!
以上のような、不動産投資に関する質問にお答えします。
マンション経営を始めたいけれど、初期費用をどれくらい用意すべきか検討もつかないという方もいるでしょう。
一般的に、マンション経営をする場合、1部屋単位で所有する区分マンションよりも、一棟まるごと所有する一棟マンションの方が初期費用は高額になります。
初期費用が少なくて済むので、区分マンションが不動産投資として有利に見えるかもしれません。
しかし、全体的な収益性を考えると、戸数が多い一棟マンションの方が有利とも言えます。
この記事では、マンション経営に必要なさまざまな費用とその内訳について詳しく説明します。
不動産投資の初期費用について理解を深めることで、具体的なキャッシュフローを考える参考になれば嬉しいです。
それでは読んでみましょう。
マンション経営の初期費用

マンション経営を始める前に、まずは最初にどれくらいのお金が必要なのか、初期費用の内訳を把握し、ある程度の検討をつけておくことは非常に重要です。
マンション経営は、短期で運用するようなものではなく、長期的な視点で資産を運用する投資ですので、可能な限り見落としのないキャッシュフローを計画することが必要です。
キャッシュフローを考える上でも、まず最初に必要になる初期費用について9つの項目に整理しましたので、それぞれ簡単に説明します。
まず、マンション経営を始める段階でかかる初期費用について紹介しましょう。
仲介手数料
マンションの購入に際して不動産業者に支払う手数料です。金額は物件価格に応じて決まり、「宅地建物取引業法」で上限額が定められています。法律で上限が明確に決まっているため、不当な支払いを要求されることがないので安心ですね。
売買における仲介手数料の上限】
| 金額 | 仲介手数料の上限(取引金額に対する割合) |
|---|---|
| 200万円以下の部分 | 5.5%(金額の5%+消費税) |
| 200~400万円以下の部分 | 4.4%(金額の4%+消費税) |
| 400万円超の部分 | 3.3%(金額の3%+消費税) |
以上の計算で求めた金額を合計したものが仲介手数料の上限額になります。あくまでも上限なので、実際の仲介手数料は不動産会社との話し合いにより決定されます。
このように計算が複雑なので一般的には「(物件価格×3%+6万円)+消費税」を上限額として請求されるケースが多いです。
印紙代
不動産取引やローン契約において、特定の文書には「収入印紙」を貼る必要があり、これにより「印紙税」を支払うことになります。
〈不動産売買契約書(不動産譲渡契約書)の印紙税額〉
| 成約価格 | 本則税率 | 軽減税率 |
|---|---|---|
| 10万円を超える~50万円以下 | 400円 | 200円 |
| 50万円を超える~100万円以下 | 1千円 | 500円 |
| 100万円を超える~500万円以下 | 2千円 | 1千円 |
| 500万円を超える~1千万円以下 | 1万円 | 5千円 |
| 1千万円を超える~5千万円以下 | 2万円 | 1万円 |
| 5千万円を超える~1億円以下 | 6万円 | 3万円 |
| 1億円を超える~5億円以下 | 10万円 | 6万円 |
| 5億円を超える~10億円以下 | 20万円 | 16万円 |
| 10億円を超える~50億円以下 | 40万円 | 32万円 |
| 50億円を超えるもの | 60万円 | 48万円 |
この金額設定は2020年3月31日までの期間に作成された文書に対する特例措置に基づいています。2019年12月20日に2年間延長が決まったこともあります。
収入印紙を貼付した後は、印章や署名によって「消印」を押す必要があります。この消印は印紙と文書の一部にまたがる形で押されます。
消印がない場合、収入印紙の金額と同額の罰金が科され、収入印紙を貼り忘れた場合は貼付すべき収入印紙の3倍(自己申告すれば1.1倍)の金額が「過怠金」として徴収されるため、注意が必要です。
登記費用
不動産の権利関係を公示するための不動産登記に関連する費用です。
マンションオーナーに関わる不動産登記は主に以下の3種類になります。
- 所有権保存登記:オーナーの建物所有権のための登記
- 抵当権設定登記:抵当権設定のための登記。銀行でローンを組むときに必要
- 建物表題登記:新築マンションの存在を公的に表示するための登記
所有権保存登記は任意ですが、ローンを組む場合には必要なので、ほとんどの場合、所有権保存登記と抵当権設定登記はセットで行われると考えて良いでしょう。新築マンションの場合、建物表題登記も重要です。これを行わないと法的に存在しない扱いになってしまいますので、建物が完成してから1か月以内に登記しないと、10万円以下の過料が科せられます。
登記にかかる費用は、物件の価格によって異なりますが、5000万円の物件の場合、約30万円から50万円程度かかることが一般的です。また、登記には多くの書類や手続きが必要で、通常は司法書士に委託します。さらに、建物表題登記以外の登記には「登録免許税」もかかります。
建築確認申請等手数料
一棟マンションを新築または増築する場合に必要な手数料で、設計図や仕様書の提出に関連します。
ローン手数料
不動産投資ローンを組む際に発生する手数料で、借入額に応じて変動します。
火災保険
一部の場合、ローン組む際に火災保険への加入が義務付けられます。
火災保険は、マンションが火災、落雷、強風などの被害を受けた場合に、その損害を賠償する保険です。この保険は、マンションそのものだけでなく、家具や家電などの家財や、機械設備なども対象になります。
一方、地震保険は、地震による建物の崩壊や火災被害、そして津波や火山噴火による被害までをカバーする保険です。ただし、地震保険に加入するには、まず火災保険に加入していることが必要です。
最近では、地震のリスクが高まったり異常気象が増えたりしているため、両方の保険に加入することがおすすめされています。そして、10年分の保険料を一括払いすることで、費用を節約できます。火災保険の場合、一般的なワンルームマンションの場合、広さによりますが、10年契約で約5万円前後が一般的です。ただし、保障内容は保険会社によって異なるため、事前に詳細を確認することが大切です。
不動産取得税
マンションや土地を購入する際には、「不動産取得税」という税金がかかります。この税金の税率は通常4%で、支払い額は「固定資産税評価額×4%」で計算されます。
ただし、2021年3月31日までに取得した場合、税率は3%に軽減されます。さらに、新築住宅の場合、1,200万円(認定長期優良住宅の場合は1,300万円)の控除が適用されます。ただし、この特例は2020年3月31日までのものです。
不動産取得税は、物件を購入した直後に支払うものではなく、購入してから半年から1年半後に請求されます。そのため、支払いに備えて資金を用意しておくことが重要です。
建築費用
新築マンションを建てる場合にかかる建築費用です。木造、鉄骨、鉄筋コンクリートなどの選択により費用が変動します。
その他の費用
建築面積の割合を考慮した建築面積の建設や駐車場、フェンス、街灯など、物件の価値向上のために必要な設備にかかる費用も考慮する必要があります。
これらの初期費用を計画し、十分な資金を用意しておくことが、マンション経営を成功させる鍵です。
初期費用が準備できない場合
マンション経営を始める際、基本的には初期費用の準備が不可欠ですが、初期費用は高額なものが多いため、準備することが難しい場合もあるでしょう。
初期費用が準備できないからといって、不動産投資を諦める必要はありません。初期資金を準備できなくても不動産投資を始める方法はたくさんあります。
初期費用が準備できなかった場合に不動産投資を始める方法について紹介します。
フルローン(頭金なし)での不動産投資
自己資金を全く用意せず、頭金を支払わないで不動産投資を始める方法が存在します。
これは「フルローン」と呼ばれ、購入代金全額を金融機関からの融資でまかなう方法です。
自己資金を持っていなくてもスタートできる魅力的な選択肢ですが、そのデメリットにも注意が必要です。
フルローンのデメリット
フルローンを選ぶ場合、借入額が大きくなるため、利息負担や総返済額が増加します。
借入金が多いと金利の変動に敏感になり、リスクが高まります。
また、物件を売却しても、ローンが残る可能性があるため、慎重なキャッシュフロー計画が必要です。
このようなことを踏まえて、通常フルローンの審査はオーナーの安定収入や金融履歴などが基準となり、審査が厳しいこともあります。
フルローンが利用できた場合に注意するポイント
購入代金をフルローンでまかなえたとしても、不動産取得税や登録免許税など、不動産投資にはその他の費用が発生します。
自己資金を持たずにフルローンを活用する場合でも、空室リスクへの備えやリフォームに対応するために、少なくとも新築マンションの場合は購入価格の10%、中古マンションの場合は20%程度の自己資金を用意しておくと安心です。
このように、自己資金が不足していても、計画的なアプローチとリスク管理を念頭に置いて、不動産投資をスタートできる方法が存在します。
そして、この場合は特に、マンション経営におけるリスクにも注意を払い、長期的な視点で物件選びを行うことが成功のカギです。
マンション経営において、継続的に発生する費用
物件を運営し続けるためには、ローンの返済だけでなく、様々な維持費用がかかります。
これらの費用を無視すると、運営に支障をきたす可能性があるため、キャッシュフロー計画にはこれらの費用を含めることが不可欠です。
以下で、毎月発生する費用と必要に応じて発生する費用について説明します。
- 共用部分の光熱費
- 修繕費やリフォーム代
- 管理費や仲介手数料
- 税金
共用部分の光熱費
マンションには「専有部分」の住居や事務所といった個別の部分だけでなく、「共用部分」も存在します。これには階段やエントランスなどが含まれます。
共用部分の光熱費や水道代は、オーナーが管理する必要があり、毎月支払う必要があります。
清掃費や保守点検にかかる費用もオーナーが負担します。
共益費として入居者に負担させる場合もありますが、バランスを考えることが大切です。
修繕費やリフォーム代
建物や周辺設備に損傷が生じた場合、修繕費用がかかります。
また、入居者が退去した際には、原状回復のためのリフォームが必要です。
これらの費用はオーナーが自己資金から支払います。
大規模修繕のための「修繕積立金」は、毎月積み立てられ、一棟マンションでは1人のオーナーが単独で積み立て、区分マンションではオーナー全員で積立金を出し合うことが一般的です。
リフォーム代は、入居者が入居時に支払う「敷金」から充当されることがあります。
管理費や仲介手数料
多くの場合、マンションの維持管理は管理会社に委託されます。
これには建物管理や入居者管理が含まれます。
管理費は管理会社によって異なりますが、通常、家賃の5%程度です。
また、不動産会社が入居者を紹介した場合、入居者から徴収された「仲介手数料」が支払われます。
仲介手数料は家賃の半月分が一般的です。
税金
マンションの敷地や建物はオーナーの資産と見なされ、毎年「固定資産税」が課せられます。
固定資産税は所有者が1月1日時点で支払うもので、「固定資産税評価額×1.4%」で計算されます。
ただし、2020年3月31日までに建てられた新築住宅で条件を満たしている場合には当初3年もしくは5年、軽減特例により2分の1に減額されます。
さらに、市街化区域内にあるマンションは「都市計画税」も支払う必要があります。通常、税率は0.3%で、計算方法は固定資産税と同じです。
ただし、都市計画税の軽減特例は土地にのみ適用され、建物には適用されません。
また、所有するマンションの数が5棟あるいは10戸以上となるか、年間事業所得が290万円を超えると、「事業税」が課税されることになります。マンション経営は不動産貸付業に該当し、税率は5%です。
マンション経営における物件管理方法

マンション経営には、建物の管理と入居者の管理を自分で行う方法以外にも、管理会社に仕事を頼んだり、別の人に部屋を貸す契約を結んだりする方法があります。
それぞれに良い点と悪い点がありますので、自分に合った方法を選ぶことが大切です。
主な管理方法3つの特徴をそれぞれわかりやすく説明します。
- 管理会社にマンションの管理業務を委託する方法
- マンションを業者に貸し出すサブリース契約
- 自分ですべてを管理する方法
管理会社にマンションの管理業務を委託する
この方法では、建物管理と入居者管理を不動産管理会社に委託します。具体的な業務には、建物の清掃や小規模な修繕、入居者の募集と家賃回収などが含まれます。オーナーは意思決定と会計業務に専念し、収益を得ることができます。この方法のメリットは、手数料に対する費用対効果が高いことです。ただし、一部の管理会社は、更新事務手数料やシステム料金などの別途料金を請求することがあります。
マンションを業者に貸し出すサブリース契約
サブリース契約とは、マンションをサブリース会社に借り上げさせて、その会社が入居者に転貸する方法です。実際には、入居者が住んでいなくてもサブリース会社に貸し出している状態となり、一定の家賃収入が確保されるメリットがあります。ただし、通常の入居者から受け取れる家賃よりも低くなることがデメリットであり、人気のある物件であれば、機会損失のリスクがあることに留意が必要です。
自分ですべてを管理する
この方法では、オーナーが自分ですべての管理業務を担当します。手数料が発生しないため、支出を抑えることができる最大のメリットがあります。ただし、入居者の募集から共用部分の清掃まで、あらゆる維持管理業務を自分で行う必要があります。マンションの規模が大きいほど、手間と時間も増えるため、不労所得を得る目的には向かないかもしれません。一人で管理できる範囲なら可能ですが、本業としてマンション経営を行っている場合に適しています。
不動産の運営が困難になった場合の対処法
マンション経営が順調でなく、入居者が全くいない状況に陥った場合、空き家として物件を放置すると、建物や設備の老朽化が進行し、最悪の場合、「特定空き家」として指定される可能性が生じます。ここでは、空き家を放置することに伴うリスクと、やむを得ず物件を売却するケースについて考えてみましょう。
特定空き家に指定された場合
マンション経営が難しくなり、所有物件を長期間空き家として放置すると、「空家等対策特別措置法」に基づいて、市区町村から「特定空き家」として指定される可能性がある点に警戒が必要です。
特定空き家とは、倒壊の危険性や衛生上・景観上の重大な問題を抱える建物を指します。特定空き家に指定された場合、以下の制約事項が適用されるため、注意が必要です。
- 固定資産税の優遇措置が解除される
- 立ち入り調査を拒否した場合、最高で20万円以下の過料が科せられる
- 修繕命令を無視した場合、最高で50万円以下の過料が科せられる
空き家を放置することのリスク
物件を空き家として放置すると、行政処分を受けるリスクだけでなく、民事訴訟や刑事訴訟にまで発展する可能性があることに留意が必要です。
通常、空き家は倒壊や火災の危険性が高まり、近隣住民の生命や財産に脅威を及ぼす可能性があるため、これらのリスクを最小限に抑えるためには積極的な管理と保守が必要です。
また、木の枝が敷地外に伸び、通行者や車両に危害を加える事例も考えられます。問題を未然に防ぐため、適切な不動産管理の取り組みが求められます。
安定的かつ継続的にマンション経営を続ける
これまで、マンション経営が難しくなるリスクについてお話ししました。経営を始める際には、不本意な売却を余儀なくされるような状況を避けましょう。収益用不動産を運用する場合、収益を増やす方法を考え、変化に柔軟に対応することが大切です。マンション経営を安定的かつ継続的に行うための秘訣をご紹介します。
キャッシュフローに余裕をもたせた資金計画を立てる
マンション経営には、ローンの返済だけでなく物件の維持管理や定期的な修繕の費用がかかります。
予測できない支出にも対応できるよう、自己資金には余裕を持たせ、ギリギリのキャッシュフローに陥らないような資金計画が必要です。
たとえば、一棟マンションを所有する場合、大規模修繕には100万円以上の費用がかかることもあるため、家賃収入が黒字でもローン返済が厳しい状況に陥ることがあります。
急な出費に備え、毎月の家賃収入から余剰資金を積み立てておくことをおすすめします。
設備投資を惜しまず、入居率と家賃を維持する
マンション経営において重要なのは、家賃収入を途切れさせないことです。
高い入居率を維持することで、家賃が下落するリスクを軽減できます。
入居者にとって魅力的な物件であるため、入居率をキープするためには、設備投資を惜しまず行いましょう。
入居者が求める機能やデザインを提供し、物件の魅力を高めます。
また、周辺環境の変化に対応するために情報収集を怠らず、街の変化に柔軟に対応しましょう。
信頼できるパートナーと連携する
マンション経営において、すべてを一人で担うのは大変です。
そのため、信頼できる不動産会社と連携することが重要です。
不動産は長期的な運用を前提としているため、空室リスクや周辺環境の変化に対応できるパートナーとの連携が役立ちます。
経験豊富なパートナーはキャッシュフローのアドバイスだけでなく、入居者トラブルの解決など、さまざまな面でサポートしてくれるでしょう。
まとめ
マンション経営のオーナーは、初期費用やローン、継続的な費用、経営に伴うリスク、管理方法の選択、そして不動産特有の様々な課題に取り組む必要があります。
充分なノウハウがなければ、リスクの予測や対処が難しいため、信頼できるパートナーと連携することが、安心してマンション経営を行うことの助けになるでしょう。

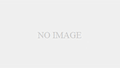



コメント